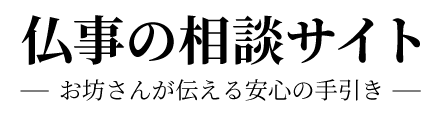初めての方
「かけがえのない人を見送る、たった一度のお別れだから。後悔のないよう、大切なポイントを確認しておきましょう。
お葬式は、故人に最期の感謝を伝える大切な場です。
参列される方々にも、その想いを届ける機会を持っていただき、皆様のお話に耳を傾けることで、改めて故人を深く知り、心からの“ありがとう”をお伝えしたいと願っています。
葬儀を行う理由に、ひとつの正解はありません。
それは、故人を偲ぶ心や感謝の形が、人それぞれに異なるからです。
仏教では、葬儀は「葬送儀礼」と呼ばれ、 臨終から四十九日、一周忌へと続く一連の祈りの営みを指します。
単なる別れではなく、 この世で結んだご縁に感謝し、故人の旅立ちを見送るための大切な修行の場とされています。
限られた時間の中で、故人の人生を振り返り、 いただいた恩に思いを馳せ、今ここで「ありがとう」を伝える—— それが葬儀の本質です。
生前に感謝を伝えることが理想ですが、 叶わぬ想いを届けるためにも、葬儀は大切に営まれてきました。
葬儀とは、命のつながりに感謝し、 生きている者が次の歩みへ心を整える、尊い仏縁の場なのです。
大切な人を亡くしたとき、 深い悲しみの中で平静を保つことは、容易ではありません。
しかし現実には、葬送の段取りを進めなければならないという厳しさもあります。
慌ただしく流されてしまいがちな時だからこそ、一度立ち止まり、冷静に考えることが求められます。
故人を、どのような形でお送りするのが最もふさわしいのか。 心を込めて見送り、後悔のない別れにするために—— 最良と思える葬送の形を、しっかりと見極めることが大切です。
喪主の決め方
一般的に、喪主の第一候補は故人の配偶者です。
配偶者がすでに亡くなっている場合や、高齢、体調がすぐれない場合には、子ども(たとえ他家へ嫁いでいる場合でも)が喪主を務めることができます。
もし子どもが未成年であれば、親族の中から後見人が喪主を代行することになります。
また、故人に近い親族がいない場合は、友人代表や世話役代表といった、親しい方が喪主を務めることもあります。
- 焼香順、席順、供花の位置を決める
親族の着席位置は、血縁関係を考慮しながら決めます。
お焼香の順番にも配慮して席順を整えておくと、式全体がスムーズに進行します。
また、供花の位置も、故人との関係性に応じて適切に配置しておきましょう。 - 弔電の拝読順と読み方の確認
いただいた弔電に目を通し、故人との関係性やご縁を考慮しながら拝読する順番を決めます。
お名前や会社名の読み間違いを防ぐため、ふりがな(ルビ)を振っておくと安心です。 - 通夜・告別式当日の振る舞い
弔問・会葬の受付が始まる頃には、身支度を整え、所定の席についておきます。
挨拶に来られる方には丁寧に対応し、式中には焼香動線に合わせて移動し、立ったまま一礼(立礼)で応えると、より礼を尽くした振る舞いとなります。 - 焼香時・僧侶退場時の心配り
僧侶による読経中、一般参列者がお焼香を行います。
その際、遺族に一礼をされるので、喪主やご遺族は目礼で静かにお返しします。
また、僧侶が退場される際には、供養いただいた感謝の意を込めて、黙礼を行いましょう。 - 参列者への挨拶
お通夜では個々への挨拶が中心になりますが、告別式の出棺前には、皆様に向けた挨拶をするのが一般的です。
悲しみが強く重荷でありそうな時は、親族代表が行うなどの気遣いも必要です。